|HOME
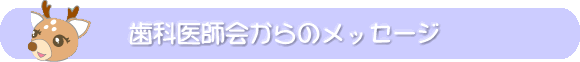
最近、スローフード、ロハスと云った言葉を良く聞くようになりました。今までのファー
ストフード、高度経済成長といった健康習慣や生活習慣を考え直してみようという動きが広
まってきています。今回はスローフードに関して考えてみます。
スローフード運動は1986年に北イタリア、ピエモンテ州のブラという小さな村から始まっ
たものです。
スローフードの「スロー」とは、だらだらと、やたら時間をかけて食べようということで
はなく、ふだん漠然と口に運んでいる食べ物を、ここらで一度じっくり見つめ直してみては
どうか、という提案です。そしてそうすることで素材や料理について考えたり食事を共にす
る人との会話を楽める生活を大切にしましょう、という考えのうえに成り立っているのです。
最初の国際大会となったパリ大会での「1989年スローフード宣言」を読んでみましょう。
工業文明という旗印のもとに生まれ育った私たちの世紀は、最初に自動車を発明し、それに
よって生活モデルを形づくってきた。
私たちはスピードに束縛され、誰もが同じウイルスに感染している。私たちの慣習を狂わ
せ、家庭内にまで入り込み、「ファーストフード」を食することを強いる「ファーストライ
フ」というウイルスに。
今こそ、ホモ・サピエンスは知恵を取り戻し、人類を絶滅に向かわせるスピードから自ら
を解放しなければならない。ここでファストライフという全世界的狂気に立ち向かい、落ち
着いた物質的よろこびを守る必要がある。この狂気を効率とはき違える多くのやからに対し
、五感の確かなよろこびを適度に配合した、ゆっくりと楽しみを持続させながら打つワクチ
ンを私たちは推奨する。
食卓で、「スローフード」を実践することから始めよう。ファーストフードの没個性化に
対抗し、郷土料理の豊かさと風味を再発見しよう。
生産性という名のもとに、ファーストライフが私たちの生活を変貌させ、環境と景観を脅
かしているとすれば、スローフードこそ、今日の前衛的回答である。
真の文化は味覚の貧困化ではなく、味覚の発達にこそあり、そこで歴史や知識やプロジェ
クトが国際交流することによって文化の発展が始まる。
スローフードは、より良い未来を約束する。
カタツムリをシンボルとするスローフード運動は、その遅々たる歩みを国際的運動にする
この宣言は、1989年 パリ国際大会にて採択されました。
では、「スローフード運動」とは、具体的にはどのようなことをしているのでしょうか?
それには、大きく別けて3つあります。
1つは、消えつつある郷土料理や質の高い食品を守ること。2つめは、質の高い素材を提供
してくれる小生産者を守っていくこと。3つめは、子供たちを含めた消費者全体に、味の教育
を進めていくことです。
歯科医の立場としてはこの活動の中では、子供たちへの味の教育が一番興味深いものです。
人類は誕生して家族という単位で生活し始め、子供たちは調理を手伝うことによって様々な
食材に触れ、大人と同じ食べ物を食べて自然と味覚を身につけていきます。例えば、「苦い」
とか「辛い」という味覚は、始めは子供には受け入れられないものです。それを幾度か口に
することによって美味しいと思えるようになり、味覚を発達させていきます。しかし、この
味覚を覚えていかないと簡単に受け入れられる甘いものばかり食べるようになってしまいま
す。
とくに現代の子供たちは、朝食は摂らないかもしくは菓子パンだけですませる、おやつは
コンビニで買ったファーストフード、夜は塾などの時間に合わせて親と別のものを食べると
いった光景が多く見られます。このことにより子供たちの食が画一化してしまい、個食化に
よって味覚を発達させるということが難しくなってきていると言われています。
また、噛むことにおいてもファーストフードの多くは軟らかいものが多いため、よく噛む習
慣がつきにくいとも言われています。
よく噛むということが良いのは良く噛むことによって虫歯を防ぐ働きのある唾液が多く出ま
す。この唾液は弱アルカリ性のため虫歯菌が産生する酸を中和し虫歯の発生を抑え、またカ
ルシウム成分も含まれているため少し脱灰(歯の表面のカルシウム成分が溶ける事)して虫
歯になりかけた歯を元に戻す再石灰化という働きもあります。
それ以外にもあごの発育を促し、口の周りの筋肉をきたえ歯並びを良くしますし、ダイエッ
トにも効果があります。
どうしてダイエットに結びつくかといえば、よく噛むことによって食べ物が小さく細かくな
り表面積が増して、消化酵素を含んだ唾液とよく混ざり消化吸収が早くなります。吸収が早
いと太ってしまいそうですが、吸収が早いということは血液中の血糖値が早めに上がるとい
うことで、そのため満腹中枢が刺激され、脳から『もう食べなくてもいいよ』という指令が
早い時期に出されるので、結果的には小食になります。
それと噛むことにより口の周りの筋肉を使いますので、時間をかけてゆっくりと食べること
は運動していることになってカロリーの消費につながります。また口の周りの筋肉にある
「覚醒反射」が刺激され体中のいろいろな働きが活発になりますので、基礎代謝が上がり、
食べても太りにくい体質になる可能性があります。
普段何気なく食事をしている習慣にも気をつければ体質をも変える力があります。
大人も子供も忙しい今日においては、スローフードを実践することには困難が伴うのでしょ
うが、食事をするということをただ単に栄養を取る行為だけと考えるのではなく、それ以外
にも家族や友達と食事をすることによって、心にも栄養をつけることができると考えるのは
いかがでしょう。
この機会にもう一度食事について考えてみるのも良い機会ではないでしょうか。
|HOME