|HOME
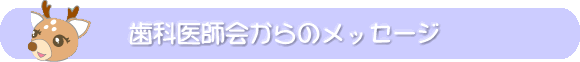
嚥下障害とは咽頭から胃への輸送の障害により食べ物を飲み込むことが困難になるこ と。
「器質的か機能的か」「食道前嚥下障害か食道性嚥下障害か」など分類の仕方や治療方 法は、さまざまですが簡単で理解しやすい内容を書きました。
加齢と嚥下機能の低下
○歯牙の欠損による咀嚼力の低下
○嚥下に関与する筋の筋力低下
○唾液の減少や味覚の低下
○喉頭の下降により嚥下反射の際の喉頭挙上が不十分
○脳機能低下による神経機能の全般的な不活性化
嚥下障害の早期発見のポイント
○発熱を繰り返す
○喉や肺の雑音
○炎症反応がでる(白血球の増加)
○痰の増加
○よだれの増加
○体重の減少(栄養不良)
○食欲低下
○胃食道逆流
高齢者における誤嚥性肺炎は、睡眠中に微量の口腔内常在菌を下気道に吸引して起こ
す不顕性誤嚥が大半です。
69歳以下では誤嚥の関与する肺炎はわずか11%であったのに対し、70歳以上では60%
に達するというデータが出てます。
誤嚥性肺炎を疑う背景には逆流性食道炎、経鼻経管栄養、食事中のむせ、歯周炎と
いったさまざまな要因があり、これらは高齢者に多いといいます。
誤嚥性肺炎の予測因子
○口腔乾燥
○口腔ケアの不備
○う蝕が5歯以上
○経管栄養
すなわち 誤嚥性肺炎の予防と改善は口腔ケアがもっとも重要です。
また口腔ケアは清拭ではなく口腔リハビリテーションを実施することです。それによ
り嚥下機能の改善は十分に期待できます。
2006年4月介護保険の新施策として地域支援事業と新予防給付が打ち出され口腔機能の向上
支援が大きな柱となり歯科医療従事者がその役割をにない介護予防に貢献するため奈良県
歯科医師会でも関係諸団体と協力して全力で取り組んでいます。
|HOME